
| ARC浮世絵ポータルデータベース/Ukiyo-e Portal Database詳細情報表示 | 1件の内1件目を表示中 | ImageNote | UserMemo |
|
クリックして画像のみのウィンドウを別々に開く→ |
縦A | 縦B | 縦C | 縦D | 縦E | 縦F | 横G | 横H |
| 同板作品表示 | 新規検索 |
| サムネイル一覧 | 簡易情報付一覧 | ArtWiki | English» |
| AcNo. CoGNo. AkoRH-R0545 AlGNo. AkoRH-R0545 |
|
絵師:
国貞〈1〉
()
落款印章:
五渡亭国貞画
絵師検索
彫師: - 人物検索 画中人名: - 人物検索 |
| 判型: 大判/錦絵 続方向: 作品位置: 001 枚組の 001 番目 03 枚続の 01 枚目 |
| Col重複: 1 All重複: 1 |
| 板元文字: ゑ |
| 改印: 極 出版年月: 文政10 (1827)・07・ 出版地: 江戸 同時作品 |
|
作品名:
「奴丸助 坂東三津五郎」
やっこまるすけ? ばんどうみつごろう yakkomarusuke bandoumitsugorō |
| 上演年月日: 文政10(1827)・ 07・26 場所: 江戸・ 市村座 興行年表 |
|
興行名:
仮名手本忠臣蔵
かなでほんちゅうしんぐら
外題: 仮名手本忠臣蔵 かなでほんちゅうしんぐら 場名: 八段目 所作題: 縁花旅路の娵入 えにしのはなたびじのよめいり : 常磐津 |
| 配役: 加古川下部丸助 〈3〉坂東 三津五郎 役者DB |
| 組解説:画中文字に「影法師踊」とある。全身黒ずくめの扮装となった団十郎が影を演じるもの。同じ時の絵に、G№100-0717、G№100-0706があり、後者に団十郎が三津五郎の影に扮する踊りの様子が描かれている。「影法師踊」がこの当時一般に普及していたか否かは定かではない。宴席での影絵遊びは江戸初期からあるが、身体全体の動きで影を作るという意味では、滑稽本『和蘭影絵/於都里綺』(文化7刊、一九作、ARChay03-0674)等との影響関係があろうか。詞章は都々逸を取り入れたもの。 |
| 組備考: この時の団十郎の黒ずくめ姿をさらに発展させたものが、翌文政11年市村座「連吉野初音旅路」(G№002-1635)か。団十郎・三津五郎が角助、丸助という本図と同様の役名で、身振芸の舞踊を行っている。 |
| 個別解説:この時の団十郎の黒ずくめ姿をさらに発展させたものが、翌文政11年市村座「連吉野初音旅路」(G№002-1635)か。団十郎・三津五郎が角助、丸助という本図と同様の役名で、身振芸の舞踊を行っている |
| 個別備考:文政6年正月『役者多見賑』三津五郎評に「別して大評判は八つ目道行となせで 路考丈の小浪をつれて出 早替り奴可内にて路考丈の女馬士との所作大でき大当り 此一まくにて無類の大入はお手がら/\[ヒイキ]此やうなおもしろい道行は又と見られぬきつとかんしん/\」とある。参考;『エンパクブック』115 2019年 |
|
画中文字: △みやれ丸助かふみた所は何とよい気色ではないか○サア/\一ぷく吸付たがよい△コリヤたましいを落し付てやけどをせぬよふに気を付ろヨ○ナニサお身のどをこがさぬ用心しろヨ△サテ此気色を見ろ こゝで小なか…… 続きを縦書でみる |
| 系統分類: 役者絵 画題: |
| 所蔵:赤穂市立歴史博物館 資料部門: 浮世絵 |
| Permalink: |
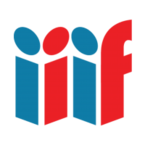
|
|
所蔵資料の利用に関しましては所蔵資料ご利用ガイドをご覧ください。 |